イベント「短編アニメーション作品の近年の成功例」レポート
- 登壇・文
- 土居伸彰・田中大裕
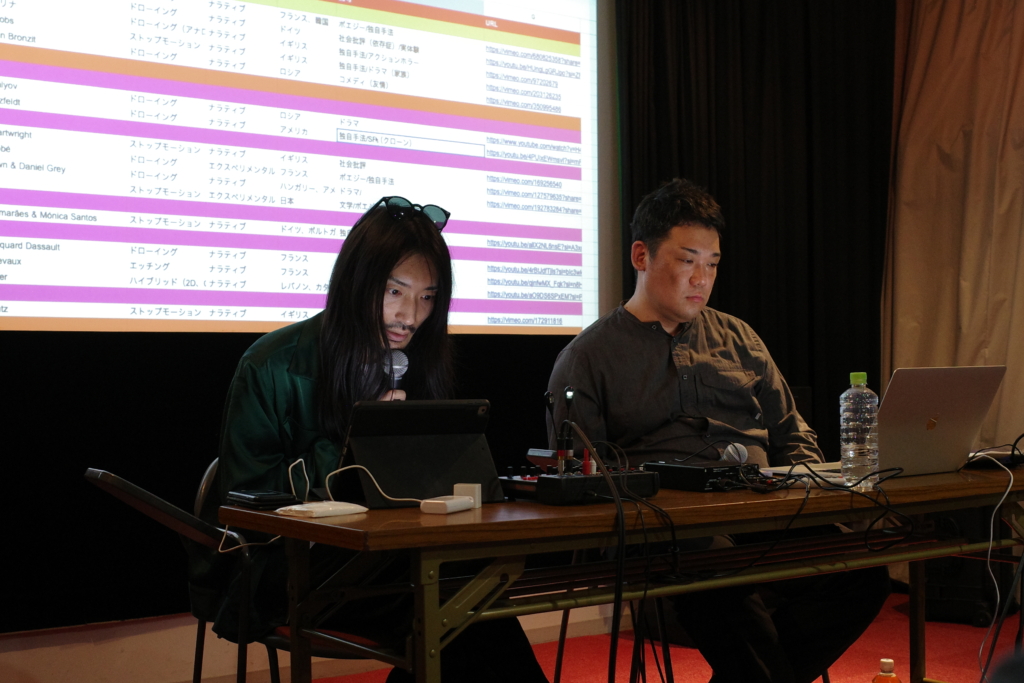
2025年5月15日、オンライン配信にて開催されたNeW NeWコミュニティ・スクールの第1回イベント「短編アニメーション作家と”成功”」。第一部に続き行われた第二部「短編アニメーション作品の近年の成功例」の採録をお届けします。講師として第一部から引き続き「NeW NeW」総合プロデューサーの土居伸彰が登壇。さらに第二部からは同事業コーディネーターのほか、新千歳空港国際アニメーション映画祭でプログラムアドバイザーと選考委員を務める田中大裕が加わります。イベント参加者に共有された「過去10年間の短編アニメーション成功例」リストを元に、当事業が考える「成功」の定義や、アワードや映画祭における過去10年間の入選・受賞作品の傾向について話されました。
はじめに:120作品リストの意図と見方
土居伸彰(以下、土居): それでは第二部を始めたいと思います。ここからは、このプログラムのコーディネーターであり、新千歳空港国際アニメーション映画祭のプログラマーも務める田中大裕さんと一緒に、ここ10年間の短編アニメーションの動向について、事前に皆さんに共有した作品リスト(※)を見ながら考えていきたいと思います。
(※編集部注:ここで言及されている「この10年間の注目すべき短編アニメーション120作品リスト」は、2014年から2024年を中心に、海外の主要映画祭で実績を残した作品や特筆すべき動向を示した作品をリストアップしたもので、多くはオンラインで視聴可能なリンクが付いている。講演後、参加者に共有された。)
田中大裕(以下、田中): ご紹介ありがとうございます、田中です。新千歳空港国際アニメーション映画祭では、毎年2000本以上の応募作品を観ていますので、その経験を元にお話しできればと思います。
まず、お手元のリストについてですが、全部で120作品あります。このリストにある作品の多く(7~8割程度)は、配給会社や制作会社、あるいは「The New Yorker」のような海外メディアや、「Short of the Week」といった短編フィルムのネットワークによって、正規に全編が公開されています。一部、予告編のみのものや未公開のものもありますが、その多くも2~3年以内に全編が公開されると思われます。
ですので、「映画祭で上映される作品がネットで公開されないことについてどう思うか」というご質問もありましたが、結論から言うと、実は映画祭にとどまらず、多くの作品がオンラインで観られる状況にあります。
土居: ただ、オンラインでの公開が長編映画やシリーズ作品と同じように話題になるかというと、なかなか難しい部分はありますね。
田中: そうですね。「源泉かけ流し」のようにどんどん公開されてはいるものの、しっかりとした広報があるわけではないので、情報が流れていってしまいがちです。Vimeoのキュレーションチームがアルゴリズムを利用せずに全て手動でピックアップしている「Staff Picks」は、良質な作品を見つける今なお有効な手段だと思います。このリストの作品の半分以上は、Staff Picksに選ばれているんじゃないかと思われます。
リストの選定基準と構成:この10年をどう切り取るか
田中: このリストは、私と土居さんで作品を出し合い、最終的にキリのいい120作品に絞りました。もちろん、これ以外にも重要な作品はたくさんあります。原則としてここ10年(2015~2024年)の作品ですが、2014年の作品でも、その後の10年を占ううえで重要な作品をいくつか加えています。
土居: 短編アニメーションが映画祭を巡回するのは約2年かかることが多いので、2015年に評価された作品でも、実際には2014年に完成しているケースも考慮しました。
田中: リストは完成年ごとに並んでいますが、公開年とはギャップがある場合もあります。また、リスト内では参考までに、以下のトピックに分けて整理しています。
- 中堅・ベテラン作家の新たな代表作:すでに充実したキャリアを誇る作家の新たな代表作。
- 頭角を現し始めた若手作家:過去10年間で頭角を現した若手作家。ただし、映画祭での認知の拡大に比重を置いているため、実際のキャリアや年齢と必ずしも一致しない。
- 表現手法にインパクトのある作品:必ずしも作家の名を知らしめたわけではないが、唯一無二の画期的な手法で爪痕を残した作品。
- 実写系映画祭で支持を集めた作品:「三大映画祭(カンヌ、ヴェネチア、ベルリン)」をはじめとした実写系映画祭や米国アカデミー賞で評価された作品。実写系映画祭において存在感を増すアニメーション作品は、近年のトピックのひとつ。
- 特筆すべき学生作品:学生作品でありながら、プロフェッショナルの作品を凌駕するような受賞歴を誇る作品。
- 現代美術系の作家による作品:美術の領域からアニメーション映画に参入し、両方の領域で評価される作家が増えてきたのも、この10年間の特徴。
手法については、ドローイング(アナログ/デジタル作画を問わず)が多いですが、特に作家が自覚的にアナログの画材に取り組んでいたり、アナログ性が作品の魅力として評価されている作品には「(アナログ)」と付記しています。カテゴリーは「ナラティブ(物語性のあるもの)」と「エクスペリメンタル(実験的なもの)」に大別しました。
製作国については、近年、複数の国が合作形式で各国の助成金制度を組み合わせて資金調達を行うケースが増えており、3か国、4か国、ときには5か国合作という作品も珍しくありません。また備考欄には、各作品が評価されたポイントなども、あくまでも目安程度ですが、記載しています。
越境するアニメーション:実写、現代美術、マシニマとの融合
土居: このリストの分け方を見ていくと、実写系映画祭での支持や現代美術系、あるいはマシニマ(ゲームエンジンを利用して制作された映像)といった、アニメーションの境界を越えていくような作品がこの10年で非常に目立ったと言えます。
伝統的なアニメーションの作り方よりも、むしろこういった周辺領域から出てきた作家の方が、アニメーションというメディアの必然性や新規性を生み出すケースも多い。これがまず、表現の可能性を広げている一つの側面です。特に実写との関係で言うと、この10年で実写系の映画祭において短編アニメーションが非常に高い評価を受けることが増えました。この波は今後、長編にも訪れるでしょう。
田中: 例えばトータル・リフューザル(Total Refusal)というオーストリアのグループが制作した『Hardly Working』は、ビデオゲーム『レッド・デッド・リデンプション2』のプレイ動画編集して作られたマシニマ作品ですが、Vimeoの年間ベストに選ばれるなど、アニメーションの枠を超えて映像作品として高く評価されています。そうした境界領域の表現は、多元的に評価されやすい傾向にあるかもしれません。
土居: 10年前であれば、アニメーションといえば手描きであることが必須条件のように思われていましたが、この10年では、作家自身が一本の線も描いていなくても、アニメーション映画祭で高く評価されることが起こるようになってきました。これは非常に面白い傾向です。
Hardly Working – Total Refusal
ディレクターシップの重要性と、アートスタイルとストーリーの蜜月
田中: 例えばニコラ・ケッペンス(Nicolas Keppens)監督は、ドローイング作品の『Easter Eggs』が映画祭で高く評価されたのち、ストップモーション作品『Beautiful Men』でアカデミー賞にノミネートされています。彼は複数のクリエイターと連携しながら作品制作に臨む監督で、ビジュアルの個性よりもむしろ、ストーリーテラーとして非常に高く評価されている印象を受けます。
土居: そう、自分の描きたいものに応じて手法を選べるというのは、実はアニメーションの歴史の中でも見られる監督のあり方です。例えば、ルネ・ラルー監督は作品ごとに異なるグラフィックデザイナーと組んでいます。
以前のトークで「アートスタイルとストーリーのどちらが大事か」という質問がありましたが、アニメーションにおいては両方大事です。手法の選択が可能だからこそ、そのスタイルを使ってどういう物語を語るのか、あるいはそのアートスタイルが必然的にストーリーやテーマを導き出すのか、という点が重要になります。その融合がうまくいった時に、表現として強くなり、映画祭でも評価されるのではないでしょうか。
アナログ回帰とニューテクノロジー:二重規範の中で生まれる表現
田中: 近年、実写系映画祭で評価される作品には、作家本人の個性的なアートスタイルが際立つ、ある種「アナログ回帰」ともいえる傾向が見て取れるように思われます。一方で、マシニマもそうですが、生成AIや機械学習といった新しいテクノロジーを駆使したメディアアート寄りの作品も、賛否両論はあるでしょうが、アニメーション映画祭を含めて一定の評価を受けている印象です。このアナログ回帰とニューテクノロジーへの注目という、ある種「二重規範」と呼べるような緊張関係が、現在のアニメーション映画祭全体の特徴かもしれません。選考の現場でも、この点で意見がぶつかることがあります。
土居: 象徴的な作家として、ニキータ・ディアクル(Nikita Diakur)監督がいます。彼はドローイング作品に取り組む学生が多いRCA(ロイヤル・カレッジ・オブ・アート)出身でありながらCGを専門とし、『Ugly』(2017年)でブレイクしました。この作品は3DCGでありながら、人形劇のように見えないコントローラーでキャラクターを動かしたり、風や水の流れといった流体シミュレーションにキャラクターが身を任せるような、偶然性を取り込んだ手法が特徴的でした。
田中: 彼は、機械学習を用いて自身のアバターに延々とバック転をさせるというユニークな作品『Backflip』も制作していますね。
土居: そういった、ある種の批評性やユーモアを伴ったテクノロジーとの向き合い方をする作家も出てきています。この10年間は、単なるアナログ技術だけでなく、デジタルテクノロジーとの関係性を探求する作家が非常に増えました。そして、その反動として、昔ながらのアナログ手法を用いる作家の新作が、より強く見えるという相乗効果もあるように感じます。
インディペンデントとチーム制作:個人性の追求と集団の力
田中: 近年のトピックとして、「インディペンデント」というと個人制作のイメージが強いかもしれませんが、近年はある程度の規模のチームで作られている作品も増えています。ここ10年のインディペンデント・アニメーションは、必ずしも個人制作に偏っていないという点は重要かもしれません。
土居: そのあたりはヨーロッパ型の制作システムとも深く関わってきます。様々な国のスタッフが関わることで、プロジェクトとして作品が作られ、それが結果として非常に強い表現に繋がっていく。
一方で、日本人作家が評価される要因の一つとして、そういった流れとは別に、個人性を徹底的に追求しているという側面もあります。物語があるようでないような、和田淳監督や水尻自子監督の作品が代表的です。和田監督であれば儀式や触感、水尻監督であればテキストの触感といった、映画が通常は前景化しないような部分にフォーカスすることで、独自の表現を生み出しています。
しかし、和田さんの『半島の鳥』や水尻さんの『普通の生活』も、実はチームで制作されており、作画や着彩を他者に任せる試みもなされています。「固有性の強い作家性をチームで作るにはどうすればいいか」という質問もありましたが、作り方としては、規模は違えど商業アニメと本質的には変わらない部分もあるかもしれません。和田さんは非常に詳細な指示書を文章でスタッフに出すなど、マイクロマネジメントに近い形で制作を進めていました。そうすることで、作家性を保ったまま予算規模を上げていくことも可能になります。
世界的に見ても、かつては短編しか作れなかったような作家が長編を手掛けるケースが増えています。個人のユニークなスタイルを保ちつつ、チーム制作で規模を大きくしていく。その結果として、映画祭では「長尺の短編が多すぎる」という問題も出てきていますが、これはコレクティブとして、チームとして個人制作を行うという世界的な流れの表れでもあるでしょう。
長尺化する短編と映画祭のジレンマ
田中: チームで作られ、濃密なドラマを描く20分を超えるような長尺の短編作品は、成功すると実写を含む映画祭で高く評価される傾向にありますね。
土居: 全体としてディレクター気質の作家が増えているということだと思います。ただ、それがアーティスト気質の作家が伝統的に多かったアニメーション映画祭というフォーマットにおいては、扱いが難しくなってきている。短編アニメーションのコンペティションは、60分~70分程度のプログラムで組まれるのが伝統的ですが、20分を超える作品が増えると、選べる本数が極端に少なくなってしまいます。その中で、短い作品が「これなら入れられる」と評価されるケースも出てきています。
ですから、作家として国際的な映画祭で評価される最初の段階においては、むしろ短くて強烈なものの方が、すっと入り込みやすいという側面もあるかもしれません。インドのコメディCGアニメーション『Croak Show』はまさにそんな作品の例といえそうです。
現代を映すテーマ性:ホラー、フェミニズム、そしてポスト・ドキュメンタリー
田中: 土居さんもプロデュースで携わられた水尻自子監督『不安な体』と和田淳監督『半島の鳥』は、作家のパーソナルな感覚が反映されつつも、実写系映画祭でも高く評価された代表例と思われます。私には作家本人の意図まではわかりませんが、『半島の鳥』はある種のフォークホラーとして、『不安な体』はフェミニズム的な文脈で評価された側面もあるように見受けられます。
土居: そうですね。ホラーという点で言うと、この10年の大きな特徴の一つにジャンル映画の台頭があります。かつて短編アニメーションはパーソナルなビジョンを表現するものが主流でしたが、エンターテインメント的な要素の中に作家自身の個人的な思いを乗せた作品が増えました。
特に台湾では、白色テロといった自国の歴史をベースにしたホラー作品が多く作られています。この10年は、ホラーというジャンル自体が社会的な批評性を持つようになった時代でもあり、その波がアニメーションにも来ていると言えます。
また、フェミニズムや女性性というテーマも、この10年で大きく花開きました。伝統的に女性作家が多い分野である短編アニメーションにおいて、抑圧された女性の秘められた欲望を描くといった表現は以前からありましたが、それがより先鋭化したと言えるでしょう。マルティナ・スカペリ(Martina Scarpelli)監督の『Egg』(2018年)は、この10年を代表する一本です。日本人作家では、水尻さんもそういった文脈で評価されることが多いですね。
田中: 一方で、少し勢いが落ち着いたように感じるのは、アニメーション・ドキュメンタリーという分野です。2000年代にはプライバシー保護の観点などから通常のドキュメンタリーでは難しい題材を扱いやすい点や、当事者の内的なビジョンをダイレクトに映し出す方法として、ドキュメンタリーをアニメーションで描くアプローチが隆盛しました。しかし、それが一巡し、現在は「ポスト・アニメーション・ドキュメンタリー」の時代に入ったといえるのではないでしょうか。単にドキュメンタリーをアニメーションで描くだけでは、なかなか頭角を現しづらい状況になっています。
土居: ポスト・アニメーション・ドキュメンタリーの傾向としては、かつてのように小さな声にフォーカスするだけでなく、語られる証言自体を疑っていくような、より複雑な視点を持つ作品が増えています。被害者として語っていた人物の証言の中に加害性が見え隠れするなど、一筋縄ではいかない、真実性が揺らぐような表現です。
田中: クリストバル・レオン(Cristóbal León)とホアキン・コシーニャ(Joaquín Cociña)監督の『骨』は、チリ最古のアニメーションフィルムという体裁をとったフェイクドキュメンタリーで、軍事政権下のチリの暗い歴史を扱っています。同じくチリのウーゴ・コバルビアス(Hugo Covarrubias)監督の『Bestia』は、軍事政権下のチリで国家情報局の諜報員として活動していた実在の女性の半生を、陶器のような独特な質感の人形を素材にしたストップモーションで描き、アカデミー賞の短編アニメーション賞にもノミネートされました。これらは、従来のアニメーション・ドキュメンタリーから一歩進んだ作品といえるでしょう。
土居: 素直に自身の体験を吐露する作品は力を失いつつあり、代わりにそうした経験を抽象化・寓話化したり、ジャンル映画の形式を借りたりすることで、解釈の多様性を持たせたり、批評性を忍ばせたりする。作り手側にも、より複雑なストーリーテリングが要求されるようになっています。そこには、マーケットとどう向き合うかという、作家としての生存戦略も関わっているのかもしれません。
また、歴史に題材を求める作品も非常に多かったです。エリザベス・ホッブス(Elizabeth Hobbs)監督の『The Debutante』や、アマンダ・フォービス(Amanda Forbis)&ウェンディ・ティルビー(Wendy Tilby)監督の『The Flying Sailor』は、18世紀や19世紀の原作を伝統的なアニメーションで描いています。かつて個人の内面世界を描いていた作家が、ユーモアを交えた歴史コメディのようなジャンルに展開していく動きも見られます。
一方で、移民・難民問題や、LGBTQ+、クィアといったテーマも、この10年でより直接的に描かれるようになりました。かつてはカムアウトできない状況の中で、アニメーション映画祭というコミュニティの中で暗に示唆するような表現が多かったものが、はっきりと語られるようになったのです。
結論:荒波の中で「普遍性」と「個人的視点」を貫く
土居: この10年間は、社会の荒波、技術革新の荒波、そしてマーケットの変遷にもまれる時代だったと言えるでしょう。その中で個人が何を作っていくのかという選択は非常に難しいですが、うまく立ち向かえた時に、世界に響く作品が生まれる。あるいは、そういった世間の荒波とは関係なく、強い意志で自分の世界観を打ち出す作家もまた、この10年で非常に目立ってきました。
映画祭で評価される作品というのは、普遍的な問題に対して、新しい個人的な視点で取り組んだものが多いように思います。同時代の人々が気にしていること、あるいは人間がずっと気にし続けてきた実存や記憶といったテーマに対して、作家が独自の切り口で迫っていく。アートスタイルとストーリーの融合もそうですが、「なぜこの切り口で?」と観客に思わせるような、しかしそれが戦略的ではなく、作家自身の内面から必然的に生まれてきたものであること。そして、それを最初のコマから最後のコマまで丹念に組み立て、観客の感覚や認識に変容をもたらすような作品。このリストにある作品には、そういった共通点があるのかもしれません。
そのテーマや手法は多様であっても、根底にあるのは、アニメーションを作ることを通じた、ある種の普遍的な問題への取り組みなのではないでしょうか。このリストを上から順に見ていくだけでも、何か掴めるものがあるのではないかと思います。
短編アニメーションの魅力と、マスカルチャーとの距離感
土居: さて、ここまでリストを見ながら色々な傾向を話してきましたが、田中さんは、様々なアニメーションに触れる中で、特にこうした映画祭で注目されるような短編アニメーションの魅力、あるいはマスカルチャーとの違いのようなものは、どういうところに感じますか?
田中: なかなか難しい質問ですが、やはり多様な価値観に触れられる点でしょうか。エンターテインメントとしてマスに向けて作られた作品ももちろん好きですが、そこからこぼれ落ちてしまうものは絶対にあると思います。私たちが普段あたりまえと思っている世界の見方とは異なる視点から世界を見るための「窓」のような役割を、映画祭系のショートフィルムは担っているように感じます。SNSなどで注目を集めるためにはバイラルする必要がありますが、それは言い換えれば不特定多数の価値観にある程度適応する必要があるともいえます。それとは反対に偏った視点から世界を捉えた、そうであるがゆえに強度を持つ個性的な作品に出会えるのが、映画祭の魅力だと感じています。
海外作家の躍進と、アニメーション業界のボーダーレス化
土居: なるほど。この10年で言うと、ギルツ・ジルマニス(Gints Zilbalodis)監督のような作家の登場は衝撃的でしたね。彼は本当に若い頃からCGアニメーションを作り続け、ラトビア初の長編CGアニメーション『Away』でアヌシーのコントルシャン部門クリスタル賞を受賞し、今やラトビアの国民的英雄のような存在になっています。映画祭出身だからといって、必ずしもアンダーグラウンドに留まり続けるわけではない、という良い例だと思います。
また、事前質問の中に「アニメ業界と短編アニメーション業界の境界線」についてのものがありましたが、個人的にはこの10年でその線引きは曖昧になってきていると感じています。短編アニメーション業界の中にも考え方が合わない人はいますし、逆に商業アニメ業界だからといって分かり合えないわけでもない。むしろ、「インディペンデント」という視点で見れば、両者にまたがる領域は確実にある。
例えば、サイエンスSARUのようなスタジオは、元々インディペンデントに近いところからスタートし、今や巨大な存在になっています。10年前は映画祭でよく見かけたような作家たちが、今やメインストリームで活躍している。そういった流動性が非常に高まっている時代なので、自分で活動の範囲を区切ってしまうのはもったいないかもしれません。
田中: 長編作品の話になりますが、昨年のアヌシー国際アニメーション映画祭の長編部門オフィシャルセレクションは、1/3が日本作品でした。その全てを日本の大手スタジオが手がけています。インディペンデントと商業を一様に評価するべきとまでは思いませんが、「芸術VS商業」という素朴な二項対立構造からはこぼれ落ちてしまう価値に目を向けるべき時期が来ているように感じます。
土居: そもそも日本のアニメーションは、予算規模的にはインディペンデントに近いものが多いですからね。海外のインディペンデント長編が数億円規模で作られているのに対し、日本の長編でそこまで予算をかけられる作品は多くありません。ある意味、日本は非常にコストパフォーマンスが良い国とも言えます。この点を活かせば、商業分野でももっと戦えるのではないでしょうか。
プロデューサーの役割と言語化の重要性
土居: ただ、そのためにはプロデューサーの存在が不可欠です。作家自身が自覚できていないポテンシャルを発掘し、外部との対話を仲介する。私自身もプロデュースをする際は、そういった役割を意識しています。
特に重要なのは「言語化」です。作家の頭の中にあるものを言語化することで、他者と共有可能にし、理解を得る。そして、その特性を理解した上で、どのようなアプローチで、どのマーケットに挑戦していくのかを論理的に組み立てていく。そういったことができる人が、もっとプロデューサーとして活躍してほしいと思います。
「会社員でもプロデューサーになれるか」という質問もありましたが、作家のサポートという点では、いくらでも可能です。自分の会社で企画を立ち上げるのも良いですし、そういった会社に転職するのも一つの手でしょう。
プロデューサー教育については、アーティスト教育が個性を深めるものであるのに対し、プロデューサーは経験(場数)がものを言う職種だと考えています。様々なケースを経験することで、対応できるパターンが増えていく。日本にはまだそういった場数が少ないかもしれませんが、機会さえあれば、優秀なプロデューサーはもっと増えるはずです。「NeW NeW」でも、今後はプロデューサー育成にも力を入れていきたいと考えています。
作家教育の難しさと、試行錯誤の中で見出す道
土居: 同時に、作家教育も今の時代は非常に難しいですね。誰がどう教えるかによって、作家の適性は大きく伸びもすれば、歪みも縮みもする。ただ、学校というのは限られた期間で特定の教えを学ぶ場であり、卒業後にそれをどう壊していくか、自分なりにどう発展させていくかが重要です。
モデルケースがない、どうしていいか分からないという時に、まずは誰かに入門してみる、誰かのやり方を徹底的に学んでみる、というのは意外と有効です。その中で、自分に合う部分、合わない部分、現実的に対応できない部分などが見えてくる。教えられたことを鵜呑みにせず、自分なりに咀嚼し、乗り越えていく力が求められます。
映画祭という場も、多様な評価基準が渦巻く中で、一度自分自身の立ち位置や方向性をチューニングし直す機会になり得るかもしれません。
結局のところ、一つの場所や方法に固執せず、試行錯誤を繰り返しながら、世の中の波にうまく乗っていく。転びながらも、より高く、より長い波に乗れるようになっていく。そういった形でキャリアを築いていくのが、今の時代なのかもしれません。