イベント「いかにして語り継がれるアニメーション作家になるか?」レポート(後編)
- 登壇
- クリス・ロビンソン
- 執筆・編集
- ニューディアー

2025年10月10日、NeW NeWコミュニティ・スクールの第3回イベント「短編アニメーション作家と”成功”」が開催されました。この記事では、オタワ国際アニメーション映画祭アーティスティック・ディレクターでNeW NeWアドバイザーのクリス・ロビンソン氏による講義をレポートします。記事は前後編に分かれており、後編では「書くこと」を通してクリス氏が何を学び、何を成し遂げたのかが語られています。
著者としてアニメーションを語ること
次に、物書きとしての活動についてお話します。私は「書くこと」を通じて、アニメーションを学んできたのだと思います。小さい頃から書くことには興味がありました。中学の卒業アルバムに将来の夢として「ジャーナリストになる」と書いていたほどです。
実際にアニメーションについて書くようになったのは、1996年にオタワ国際アニメーション映画祭のカタログに上映作家に関するエッセイを寄稿したのがはじまりです。先ほど「書くことで学んできた」と言いましたが、そもそも当時、インディペンデントな作家について書こうとしても、先行する書籍がほとんどありませんでした。書籍が出ているのは、フライシャー兄弟、ノーマン・マクラレン、ブラザーズ・クエイといった、すでに名前が知られている人たちだけ。だから、私はインディペンデントなアニメーション作家について書くために、自分で全てを調べて、会える人には直接会いに行きました。
実際に会ったアニメーション作家たちは、インディペンデントなシーンではかなり著名な作家でも、全くエゴがなくて素敵な人たちばかりでした。どこか少し歪んでいたり、欠けているようなところはありますが、愛らしくて「この人と家族になりたいな」と思える人たちばかりでした。その後も、機会があれば積極的に作家たちと会いました。旅先の国で良い作家がいれば会ってくれるようにお願いしたり、オタワに来る人がいれば事前に作品をビデオで送ってもらい、それを観た上でインタビューを行いました。書いたものは映画祭のカタログに収録され、のちに映画祭独自の雑誌も出すようになりました。
物書きとしての初期の私の書き方は、非常にドライでアカデミックなものでした。しかし、それはすごく狭い世界の中でお互いに向けて書いているだけのように思えて、次第に「もっと広く伝える書き方をしたい」と思うようになりました。
そんな自分の書き方を解放してくれた一冊の本があります。ニック・トーシュによって書かれた、シンガーであるディーン・マーティンの伝記(Dino: Living High in the Dirty Business of Dreams)です。ディーン・マーティンはすでに亡くなっていましたが、その伝記は、まるで本人が目の前で話しているかのようでした。文体は詩的でポエティックかと思えば、汚い言葉遣いで俗悪だったりもする。しかし、その言葉遣いだからこそ、ディーン・マーティンの本当に深いところまでが伝わってきました。
この本にインスピレーションを受けて、私もエストニアのアニメーション作家プリート・パルンについての本(Estonian Animation: Between Genius and Utter Illiteracy)を、かなり自由に書きました。あまりに自由に書いたため、私自身がでっち上げてしまった部分もあり、今となってはこの本を元に研究している人がいたら申し訳ないなと思うほどです(笑)。
物書きとして、もう一つ転機がありました。1995年頃、アヌシーでロン・ダイヤモンドという人物に会いました。彼は「世界中のアニメーション情報を集めたウェブサイトを作りたい」という夢を持っていました。その夢はやがて「アニメーション・ワールド・ネットワーク(AWN)」として実現し、その中でオンライン・マガジン部門が立ち上がることになります。
私はそこで、当時ASIFA(国際アニメーションフィルム協会)に感じていた不満をぶつけました。1960年にはじまったアニメーション映画祭の歴史は、ASIFAという作家主体の組織が中心でした。アヌシー、ザグレブ、オタワ、広島といった映画祭も、作家たちが自分たちの作品を見せるプラットフォームとしてASIFAによって立ち上げられたものです。しかし、私がオタワに関わり始めてからは、ASIFAの影響力に強い違和感を覚えるようになりました。アニメーションのシーンが変化しているのに、彼らはそれに対応できていないと感じたのです。
最初に書いたのは、ASIFAに対する怒りに満ちた記事でした。いま読み返しても「よくもまあ、こんなにひどいことを書いたな」と自分でも思うほどです! 例えば当時のオタワでは、ASIFAのメンバーは航空券さえ自分で負担すれば、滞在費も映画祭パスもすべて映画祭持ちという厚遇を受けており、それを当たり前だと思っていました。しかし映画祭の予算は厳しく、そうした不公平な待遇への不満をぶちまけたのです。結果として、オタワはASIFAから最初に抜けた映画祭となりました。
AWNでの執筆機会が増えるにつれ、怒りの記事だけでなく「お行儀のいい記事」も書くようになりました。それから、90年代後半は好景気で、あらゆる映画祭やスタジオが豪華なパーティーを開き、学生をリクルーティングしていました。そんな状況の中、自分の仕事がまるで斡旋業者、つまり「ポン引き(Pimp)」のように感じられました。そこでAWNに「アニメーション・ピンプ(The Animation Pimp)」という短い記事を書きました。「映画祭をやっている自分は、まるでアニメーション界のポン引きだ」と。これが好評で、毎月の連載コラムになりました。
2000年から2005年にかけてはとにかく書きまくりました。この時期に出会った音楽評論家リチャード・メルツァーの影響も大きいです。彼は聴いてもいないレコードをジャケットだけで評論したり、デートの経験をジャズの評論にすり替えたりするような、圧倒的な書き手でした。それに倣い、私も『アニメーション・ピンプ』でアニメーション界に対する意見や愚痴を、極めて正直に、そしてクレイジーに書いていきました。
当然、たくさんの抗議が届きました。今でも覚えているのは、アレクサンドル・ペトロフの『老人と海』についての記事です。私はこの作品が本当に嫌いだったので、どれだけ嫌いかを伝えるために、自分の周りの50人の知人の名前を挙げ、「みんなこの作品が嫌いだと言っている、自分の飼っている犬さえ嫌っている」と書き連ねました。今から考えれば単にバカバカしいのですが、当時は大真面目でした。
そうして書いているうちに、ハンター・S・トンプソンの「ゴンゾー・ジャーナリズム」に出会いました。主観的なジャーナリズムのスタイルです。一般的に、ジャーナリズムは書く人の人格が見えないよう、透明な存在として客観的に書かれるべきだとされています。しかし、それはおかしな話です。作品を見たり体験したりするのは、すべて私たち自身の人生の中のできごとです。私は、一つの決まったやり方(客観的な書き方)に従うのではなく、違う方法で考え、表現するための新たなフォーミュラ(公式)を開発しようと実験を繰り返していました。
私には明確なゴールがありました。普通とは違う方法でアニメーションを考えること、そして無名の作家を世に出していくことです。2007年には、AWNのコラムをまとめた『アニメーション・ピンプ』が、友人のアンドレアス・ヒュカーデのイラストと共に一冊の本になりました。今ではどこへ行っても「ミスター・ピンプ」と呼ばれるようになってしまいましたが、それはそれで私のキャリアの一部です。
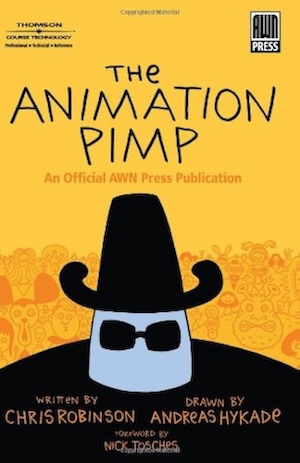
2000年、私はオタワ国際アニメーション映画祭のエグゼクティブ・ディレクターに就任しました。しかし、予算管理や人事といったすべての権限を持つこの役職は、私には全く向いていませんでした。そこで、当時の妻であったケリーに相談しました。ケリーはプロデューサーとして活躍していたので、彼女にマネージング・ディレクターを任せ、私はアーティスティック・ディレクターに専念するという二人体制を敷きました。この役割分担は大成功でした。彼女のおかげで運営は安定し、映画祭は大きく成長することができました。運営に余裕ができたことで、私はさらに執筆活動に力を入れることができるようになりました。
さらに別の出会いもありました。医療系の出版社を売却し、なぜかアニメーションの本を出版し始めたジョン・リビーという人物です。私は彼に「インディペンデントな作家たちの記事をまとめた本を出したい」とピッチし、それが実現することになりました。ジョン・リビーは「何でも自由にやっていい」と言ってくれました。私はカナダ政府の助成金をもらい、カナダ中のアニメーションスタジオを訪ねる旅に出ました。「カナダのアニメーションの現在」をまとめる企画でしたが、実際には旅の過程で出会う作家たちを遊び心たっぷりに描く紀行文のような内容になりました(Canadian Animation: Looking for a Place to Happen)。
大きなスタジオの裏側に隠れて見えなくなっているインディペンデントな作家たちに光を当てることを目的とした本も書きました。『アンサン・ヒーローズ・オブ・アニメーション(Unsung Heroes of Animation)』というタイトルで。これはニック・トーシュの『アンサン・ヒーローズ・オブ・ロックンロール』へのオマージュです。裏表紙には、かつて私に寄せられた最悪なヘイトコメントの数々を載せました。ニック・トーシュ本人にも連絡を取り、イントロダクションを書いてもらいました。彼が書いた「この本はアニメーションの本でありながら、全くアニメーションの本ではない」という一文を読んだとき、すべてを理解してもらえたと感じ、心から嬉しかったです。
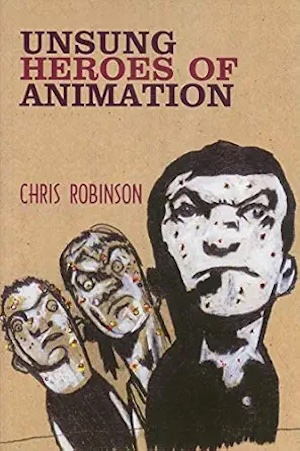
その後、日本のアニメーション作家についての本も出版することになりました。きっかけは国際交流基金からの招待でした。初めて訪れた日本は、私にとって非常に奇妙な体験でした。時間の感覚が狂い、過去と現在と未来が折り重なって共存しているように感じました。この感覚を伝えるには普通の文体では無理だと思い、1980年代のセサミ・ストリートの映画『ビッグバード・イン・ジャパン』を思い出しました。日本で迷子になったビッグバードのように、自分自身も日本で迷子になり、そこで出会うキャラクター(アニメーション作家)の頭の中に入っていく……というファンタジーのような、シュールな構成で書きました。その作家のエッセンスを読者が体験できるように工夫しました。当時村上春樹を読んでいたことも影響していますが、この本は私が物書きとして目指していた理想に最も近づけた一冊であり、非常に誇りに思っています。
実はこの来日の直前、親友が41歳の若さで急逝するという悲劇がありました。私は立ち直れないほどのショックを受けており、絶望の中で自分自身を取り戻すための旅でもありました。そうした個人的な重なりも、あの本には込められています。
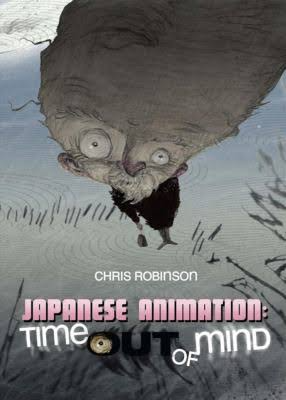
これまで多くの著書を出し、幸いにもそれらが研究のリファレンスとして使われることも増えました。私は歴史家でも批評家でもジャーナリストでもありませんが、これらの活動はすべて自分の人生と分かちがたく結びついています。
私のルーツにあるのは、子供の頃から親しんできたモンティ・パイソンなどのスタンダップ・コメディです。そこで育んだのは「反抗していい、システムを批評していい、そこに従う必要はない」という反骨心でした。
そんな中、2019年にザグレブ国際アニメーション映画祭から「アニメーション研究に関する功労賞」を授与されることが決まりました。コロナ禍を経て2022年に実際に受賞した際、私は「あ、認められてしまった」と冗談半分に思いました。それはこれまで人々を説得し続けてきた自分の活動がようやく認められたという勝利感でもありました。
私は人生を通してアニメーションに出会えたことに、心から感謝しています。こうしてお話しできたことも、私にとって大きな喜びです。本当にありがとうございました。
